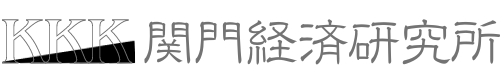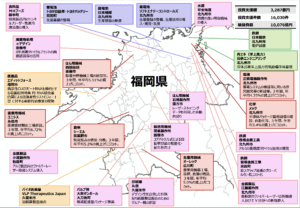化学と物理
先日、福岡市で海水を使った浸透圧による発電設備が稼働したという話を聞いて、ちょっと興味が湧きました。
調べてみると、概念自体は1976年ごろからあったそうです。
「逆浸透」って高校の化学だったか、習いましたよね。濃度の違う2つの溶液を膜で隔てると、濃度が均一になるように薄い方から濃い方へ水が移動する、とか。
津波や洪水で思い知りましたが、非圧縮性である水のパワーは半端ない。体積次第では悪くない発電方法なのかも。
濃度差ってそんなにエネルギー持ってるんだっけ。
液体の状態方程式みたいなのがありました。こっちは物理。うろ覚えです・・・。
πV=nRT=(w/M)RT から、浸透圧π=(w/M/V)RT
浸透圧が得られるので、E=PVに当てはめてπVでいいのかな・・・。いや、違う気がする。
やっぱり浸透圧がヘッド相当だと考えれば、mgπ/p0なのかな。
全然わからんくなってきた。
うーん、数値のイメージも湧かん。
今回のプラントでは出力は230kWでした。
膜で隔てた水との差によって得た圧力でタービンを回すのですが、効率を上げるために海水側は加圧しているらしい。海水も濃縮して使っているようで濃度は8%だそうです。
半分くらいのエネルギーは加圧で消費するようだし、濃縮にも必要でしょうから、なんとなく微妙ですな。
でも、時間や天候に限りがある太陽光よりは効率は良さそうだし、何よりも再生可能エネルギーの可能性がどんどん増えるのは歓迎。
式がどうなるかは、GPTに聞いてみます。