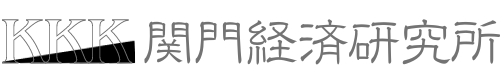グリッド
昔、SOFCに絡んでいた際にちょっと学びました。
マイクログリッドでしたね。小型の燃料電池を個別分散で配置しつつ、系統電力に組み込んで全体として効率を上げるといった感じでしたか。
太陽光発電の普及で若干近づいたかなと思いつつも、燃料電池自体の進みのせいか、盛り上がってませんね。
同じような話で、PCの大規模クラスタリングもありました。一時期盛り上がった(気がする)けど、最近あまり聞かないかな。
でも、これだけネットワークが進んだ時代、散財しているものが仮想的に集約されて動くといったシステムがどんどん出てきてもおかしくない。
で、ちょうど面白い事例2つを発見。
ソフトバンクやKDDIが進めているAI-RAN。
携帯電話の基地局をネットワーク化してAIの処理に使うという話。
ピンとこないけど、実は基地局はハードウェア依存からソフトウェア依存に変わってきているそうで、GPUを使った汎用サーバーでも動作できるのだそうです。
つまりGPUが結構多くの地域に点在しているってこと。しかも通信の処理は常時フルじゃないですからね。余った能力をAIの計算に使うということみたい。
AIの活動が学習から推論に移ってきていることも、対応できる幅を広げている模様。
確かに、これだけ通信速度や分散処理の性能が上がってくると、いろいろなところにある機器を活用するって考えは良い気がします。
もうひとつはテスラ。マスク氏の言動や中国の不信でどうなっちゃうのかと思ってはいますが、良い活動もしてくれています。
仮想発電所(VPP)事業を日本で始めるのだそうです。
企業に無料設置した蓄電池を一括管理。再生可能エネルギーと電力需要の差に応じて、充放電する「仮想電力会社」だそうです。
最近、揚水発電が見直されたりしていますが、目的は同じ。これからの世の中では必要な技術ですね。
モノの世界だけでなく、知的ノウハウにも当てはまるかも。
人の知識が有機的につながるってのは理想かもしれません。
AIが学習してるのはあくまで過去の知識だけど、リアルタイムで生の「知」を融合させるシステムとかね。