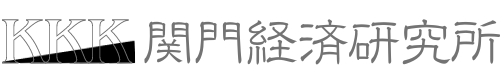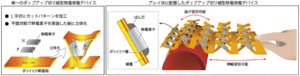AGEs 新しい経済用語?
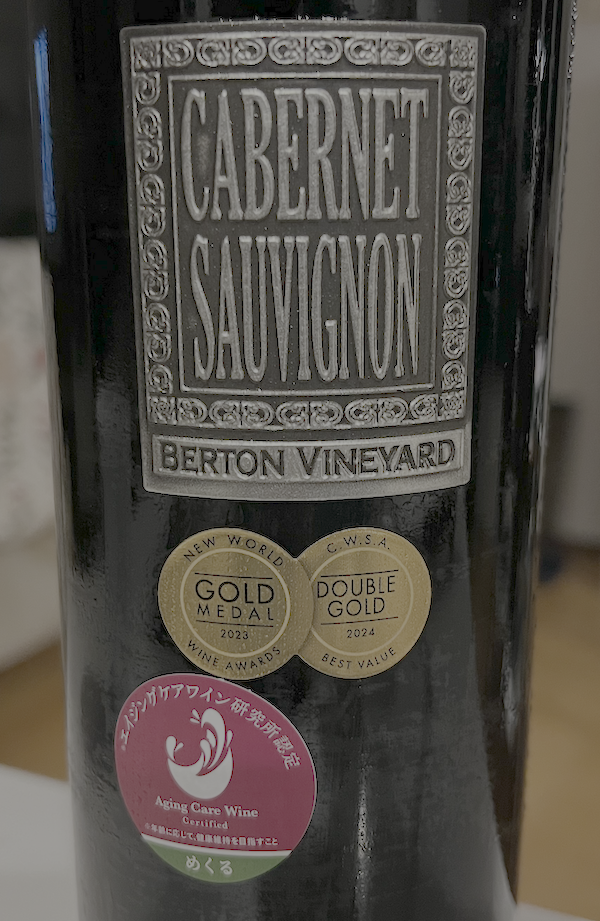
SDGsが進化したのかと思ったりしましたが、私の知識不足でした。
糖がタンパク質に過剰に結びついて変性したものは、体へのさまざまな悪影響を及ぼすとのこと。そういった物質をAdvanced Glycation End Products(終末糖化産物:AGEs)と呼ぶようです。
具体的には、炒め物でこんがり美味しいそうになった部分・・・だそうです。よく食べてますよ。分解されにくくて、過剰な蓄積がダメとのこと。
焼いたものだけじゃなく、摂取した糖が体内のタンパク質と結びついて生成されるという記載も、医美容系のHPには結構あるようですね。
なんで行き着いたかというと、昨夜のワインに「エイジングケアワイン研究所認定」のシールが。
うちも研究所ですからね、負けちゃいられない。
HPを眺めてみると、「ワインによる糖化ケア」を推進する団体。
団体そのものの詳細や沿革はあまりはっきりしないけど、具体的な認定の方法は記載がありました。
グルコース(糖)とHSA(アルブミン:タンパク質ですな)の混合物を加熱し、AGEsの量を測定。
加熱前の混合物に、ワインとアミノグアジンをそれぞれ入れたものを比較します。
アミノグアジンに抗酸化作用があることが知られているので、基準として使うとのこと。
元になる研究では、抗糖化作用の強かったワインを4週間飲んでもらい、体内へのAGEsの蓄積を検証されていました。
AGEsの蓄積量はコントロールに対して有意に減少していたそうです。
私も老化防止できたのでしょうか。デザートにチョコパイを食べてしまいましたが・・・。
認定ワインはまだ200本程度です。今後どうなるでしょう。
日本ワインなら機能性表示食品を狙うのもありだと思いますけど、インポート物中心みたいなので、ちょっと難しいかな。
どうでもいいけど、”Age”sと読めば、なるほど老化関連!