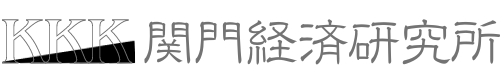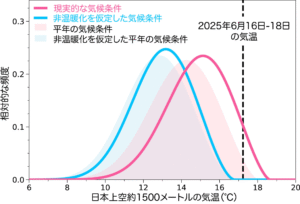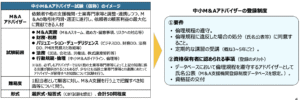IT Japan Award
先日発表されました、グランプリは、かつて仕事でお世話になった、富士フィルムHD。
ほんと、すばらしい会社です。
今回受賞したのは、「サプライヤーとの製品⽣産計画の共有から部品の発注、納⼊までのやりとりを刷新した取り組みにおいて、ブロックチェーンを採用した「サプライヤー連携管理システム」」。内製で開発されたそうです。
どこまでの情報共有なのかなと思って、ちょっと覗いてみました。
もともとは、部品の安定調達が目的のようです。コロナでサプライチェーンがぼろぼろになったところからでしょうか。
「メール/電話/FAXによる非効率かつ不確実な情報のやりとりを解消するため、信頼できるデータを中心に置いて、当事者同士がそのデータを見ながら、迅速かつ信頼できる情報のやり取りを実現した」(原文を修正)とあります。
(いやいや、FAX使ってるようなサプライヤには高度すぎませんか・・・)
そのデータの信頼性を担保するため、ブロックチェーン技術を使ったようです。
2年くらい実運用した結果、「生産計画」開示によってサプライヤーの先手管理が可能になり、「確度の高い納期回答」を受領でき、「在庫最適化」が期待できるとのこと。
さらには、AIやシミュレーションによってサプライチェーン全体での最適解をデジタル空間上で計算し、エネルギー低減、コスト削減、利便性の向上につなげるとあります。これは悪くない。
サプライチェーン全体が、バーチャルな感じで1社に集約されたイメージでしょうか。
けど、競合もぶら下がっているようなサプライチェーンの中で、各社がどこまで情報出すのかな。
最終調達元の富士フィルムの生産情報だけ開示するのではなく、供給する各階層のみなさんが情報開示するということになると、システムの問題よりも、ネックは各社の意識や、情報共有で生じるリスクや弊害への手当てという気もしますね。
昨日も、サラリーマンの頃の取引先を訪問したのですが、無理な生産や在庫確保をお願いしてご迷惑をおかけした話になりました。(ごめんなさい)
電子部品が確保できなかったり長納期になる中、〇〇ヶ月分を常時在庫してください的な注文をしたのですが、サプライヤの階層ごとに、その数字に安全分が積み上がって、末端では余剰部品が大きく増えてしまっている的な問題もあるとのこと。
なので、元になる最終メーカーの数字が見えれば、サプライチェーンの末端まで、もう少し適正な在庫確保はできるのかもしれません。
生産管理部門の方から見れば、理想的な対策の1つなのでしょう。
私としては、在庫に頼るBCPから脱却して欲しいというのが本音ですが、どんな活用状況か、今度ヒアリングしてみたいと思います。